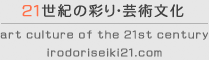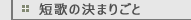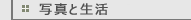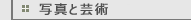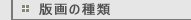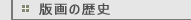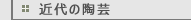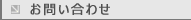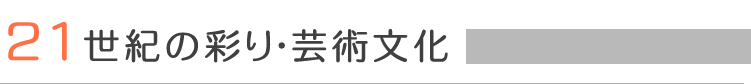◆日本の陶芸
陶芸(とうげい)
陶器と磁器を中心とする、いわゆる「焼物」の技術史的、美術史的な展開についての呼称。
陶器と磁器の分類については、各国で慣習化された概念が通用していて、一定した基準はないが、素地(きじ)(胎土)のガラス化が著しく進み、透光性があり、たたくと金属性の音を発し、吸水性のほとんどないものを磁器とし、その純化が進んでいない場合を陶器とよぶのが一般的で、両者とも施釉(せゆう)を原則としているが、厳密な識別法はないといってよい。また、施釉していない土器と、釉(うわぐすり)の有無には拘泥しない器(せっき)がある。土器と違って器はかならず窯の中で焼きしめてあり、素地は不透光性で、純白磁ではない。西洋では素地に不純物を多く含む準磁器を器に含めるのが一般的傾向であるのに対し、東洋ではこの種のものは磁器の範囲に含めるなど、これもいまのところ意見の統一はみていない。わが国では一般に陶磁器のことを、中部地方以東では瀬戸物、関西以西では唐津(からつ)と俗称することが多い。
[ 執筆者:矢部良明 ]
近代の陶芸
幕末の混乱期を経て明治維新を迎えた陶磁界は、目覚ましい技術革新を経ながら伝統様式も展開させ、世界に通用する陶磁が競ってつくられた。しかし時流を形成するような大きな動きはみられず、特筆されるのは個人陶工の作品である。宮川香山(こうざん)(1842―1916)、3代清風与平(せいふうよへい)(1850―1914)、9代帯山与兵衛(たいざんよへえ)(生没年不詳)、加藤友太郎(1851―1916)、竹本隼太(はやた)(1848―92)らが釉法を鋭意改良し、技巧主義による精巧な秀作を残している。
大正時代になると、芸術活動としての陶芸制作が楠部弥弌(くすべやいち)(1897―1984)を中心とする赤土(せきど)社のメンバーで企図され、また河井寛次郎(1890―1966)、浜田庄司(しょうじ)(1894―1978)らは民芸の旗印を掲げて新様式を樹立した。
昭和に入ると帝展や国画会に工芸部門が設けられ、板谷波山(はざん)(1872―1963)、富本憲吉(1886―1963)らが活躍、また金重(かなしげ)陶陽(1896―1967)、荒川豊蔵(とよぞう)(1894―1985)、加藤唐九郎(1898―1985)らは古陶磁を手本とする復古主義を唱えて作陶し、新旧の様式が混在する現代の陶芸界の潮流が醸成された。
[ 執筆者:矢部良明 ]
現代の陶芸
第二次世界大戦後まもない1946年(昭和21)に京都の若い陶芸家が「青年作家集団」を結成し、そのなかから走泥(そうでい)社が48年に誕生する。現代美術の多様な先進性を焼物の分野に取り込もうとする八木(やぎ)一夫(1918―79)や鈴木治(おさむ)(1926―2001)らがその代表者であった。その結果、オブジェの造形を求める焼物は彫刻ときわめて近い表現領域が開拓された。その成立に大きな刺激を与えたのは彫刻家のイサム・ノグチの作品であった。
土を素材とする非実用的なオブジェの制作は、実用という規定性がないために自由な創意が個性の赴くままに展開し、意表をつく造形物がつくられる。人間の意思、情念、感情、思惟(しい)などが形式を打破したところに表現され、長く工芸の基本造形原理であった「多様の統一」は完全に否定された。ここに人間の精神の工芸が唱導され、現代美術の重要な一分野として定着しつつある。
[ 執筆者:矢部良明 ]
参考文献
1.『世界陶磁全集』全22巻(1975〜86・小学館)
2.『日本陶磁全集』全30巻(1975〜78・中央公論社)
3.『日本やきもの集成』全12巻(1980〜82・平凡社)