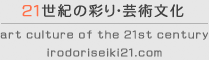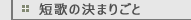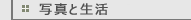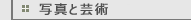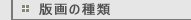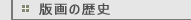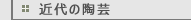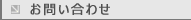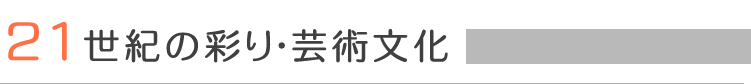◆写真の世界
写真とは
光学的な映像や、放射線、粒子線の痕跡(こんせき)を可視的な画像として固定する技術の総称であり、またそれによって得られた画像をさす。英語のフォトグラフphotographにあたり、語義はギリシア語で「光で描く」ことを意味し、イギリスの科学者ジョン・ハーシェルが、写真術の発明者の一人フォックス・タルボットの発明した紙ネガを用いる写真印画に対して、1830年代末に命名したもの。タルボットはそれ以前から化学反応を応用して光でものの影を写し取る試みを行っており、それをフォトジェニック・ドローイングphotogenic drawing(フォトジェニックは「光に由来する」の意)とよんでいた。
なお、フォトグラフィphotographyは写真を制作する行為、すなわち写真術をさす。写真という訳語は、幕末の洋学者大槻玄沢(おおつきげんたく)(磐水(ばんすい))がその著書『蘭説弁惑(らんぜいべんわく)』の下巻所収の「磐水夜話(やわ)」(1788)のなかで、写生の道具として紹介したカメラ・オブスキュラcamera obscura(ラテン語で「暗い部屋」の意)に、写生と同義語の写真という語を当てて「写真鏡」と命名したことに由来する。
写真は一般的にはレンズによって形成された像を、感光性のあるハロゲン化銀乳剤を塗布したフィルムに投影し光化学反応で潜像を得て、それに現像、定着などの化学処理を施し可視像とし、さらに印画紙へ転写する。また1990年代以降、発達が目覚ましいデジタルdigital(デジタルは「数」の意)写真は、ハロゲン化銀乳剤のかわりに感光性の半導体素子で光学像をデジタル信号に読みかえ、コンピュータによる電子的な処理を経て画像を得る技術で、応用範囲が広く、ハロゲン化銀を用いる写真技術にとってかわりつつある。
写真の活用と応用の範囲はきわめて広く、一般的な記録や記念、視覚表現のためのみならず、科学の基礎研究から工業、土木、医学、天文学、宇宙等の諸分野で学術的な利用がされている。こうした専門性の高い写真の活用は、1990年代以降、コンピュータによる画像処理技術と結び付き、またさらにデジタル写真の普及と相まって、より多様化し、その可能性を拡張しつつある。
[ 執筆者:重森弘淹・平木 収 ]
写真と生活
日本のカメラの普及率は、すでに一家に2台以上に達するといわれる。とくに1960年代中ごろ以降、操作の簡便なカメラが普及し、80年代には使い捨てカメラ(レンズ付きフィルム)も日常化し、初心者にも自由に使えるようになった。それらの使用目的の大半が記念写真や気軽なスナップ写真であることはいうまでもない。また、動画像についても小型ビデオカメラの発達が受け手としてのみの受容意識を変えたが、その点、写真は誕生期からアマチュアが創造の担い手となっており、また送り手でもあったことに注目しておく必要があろう。
記念写真が重要なのは、個人・家族・集団の貴重な時間、つまり思い出に防腐処置を施す意味があるからであり、また分身として礼拝されたり護符の役割を果たすからである。そこで記念写真は個人にとってしばしば視覚の物的な痕跡(こんせき)ですらある。一方、記念写真は私的な記憶でありながら、時間の経過とともに、時代の客観的記録として資料的価値をもつようになることも事実である。
ときには公式的な写真記録や、報道写真以上に、個人的な動機から撮影された記念写真に記録的な真実味のあふれていることがある。1970年代以降、パーソナル・メディアとしての写真のあり方が再考されるようになり、改めて個人のアルバムの発掘が盛んとなった。個人のアルバムも特定の目的に沿って一定の文脈によって再編集されることで、民衆史の視覚的な資料として再評価の対象となりだした。
個人の生活にとっていまや記念写真は欠くべからざるメディアといってよく、また私的な記憶を超えた再生産性に注目しなければならない。
[ 執筆者:重森弘淹・平木 収 ]
写真と芸術
他方、写真は芸術の手段でもある。写真は当初、もう一つの版画として、いいかえれば芸術の複製手段として歩み出したが、やがてその独自の複製技術によってのみ可能な表現領域を開拓し、複製芸術として自立するのである。しかし、写真は初期、先行芸術としての絵画に強く影響されたのも事実で、19世紀は全体的に「絵画的写真」の時代でもあった。
20世紀に入って、カメラの機能に忠実な表現、換言すれば機械的リアリズムにのっとった表現方法を自覚するに及んで、写真芸術も革新される。むろん、20世紀の各芸術ジャンルと密接に交流し、相互に影響を与え合いつつ今日に至っている。写真はマス・メディアとしての報道写真や広告写真、さらに各種の学術写真(科学・応用写真)を含む一方、純然と芸術としての写真創造の伝統を伝えている。
写真の対象は、報道、広告を問わず、人物、風景、自然、都市、風俗など、およそ人間と人間にかかわりのあるもの、レンズの及びうるものすべてにわたっている。報道や広告の写真が、その目的のためのコミュニケーションを第一義とする表現とするならば、芸術としての写真は、題材を共有しつつも、美的表象と芸術的鑑賞の対象として創作されるものである。
しかしながら、コミュニケーションや学術的な目的を第一義として撮影された写真も、「芸術としての」という文脈上から、鑑賞対象として作品視されることもしばしばあるところが特徴的である。事実、天体写真などの科学的な記録や、ドキュメンタリーの場合でも、それがわれわれの美的感性を喚起し、また人間性の真実を提示しているものは、芸術としての文脈上から、美術館に展示されることも少なくない。これは要するに、写真の記録性が新鮮なリアリティーを根底に内包しているからである。そこでこのリアリティーが他の芸術ジャンルの表現傾向に強い影響をも及ぼす原因になっている。その半面、なお「芸術としての」という文脈が流動的で確定していないことも示しており、はたして写真は芸術や否やといった議論が現在もときにおこる要因ともなっている。
1980年代以降、日本でも公共美術館での写真コレクションが始まり、写真と美術館の関係はきわめて重要な意味をもつようになった。83年(昭和58)個人の写真家の展示館として世界最初といってよい土門拳(どもんけん)記念館が作者の郷里山形県酒田市に開設された。続いて88年には川崎市市民ミュージアム、翌89年(平成1)には横浜美術館がそれぞれ写真部門を設けて新規に開館し、95年には東京都写真美術館も開館した。また東京と京都の二つの国立近代美術館も写真作品の収集と展示に着手するに至った。
今日、マス・メディアとしての写真とは別に、純粋に表現的創作的な方向を目ざす写真をシリアス・フォトとよび、ギャラリーがその主たる発表舞台となっている。これらシリアス・フォトの担い手には、専門作家のほかにアマチュアも多い。
19世紀には、欧米諸国の場合も、アマチュアが芸術写真を担ってきた。1世紀以上続いているアマチュア団体もあり、現在も数多くのグループ結社がある。コンペも盛んに行われ、写壇なるものを形成している。
[ 執筆者:重森弘淹・平木 収 ]
参考文献
1. 重森弘淹著『写真芸術論』(1967・美術出版社)
2.『写真大百科事典』全10巻(1981〜82・講談社)
3.『世界写真全集』全12巻(1982〜84・集英社)